「中学生から新しい習い事を始めるのは遅いのでは?」と感じていませんか。
結論からお伝えすると、中学生の習い事は今からでも十分に間に合います。
部活や塾との両立の仕方、目的別のおすすめ、そして失敗しない選び方までを徹底解説しました。
第1章|中学生の習い事は遅くない?今からの伸びしろを科学的に
「中学生から新しい習い事を始めるなんて遅いのでは?」と感じる方は少なくありません。
けれども結論はシンプルで、中学生の習い事は決して遅くありません。
この時期だからこそ得られる伸びしろがあり、むしろ効率よく成果を積み重ねやすいのです。
ここでは、脳・身体・社会性の発達段階を踏まえた「間に合う領域」、部活や塾と両立するための時間配分、そして最小コストで始めるための工夫について整理します。
脳・身体・社会性の発達段階からみる「間に合う領域」
思春期にある中学生は、心も体も大きく変化する時期です。
- 脳はまだ発達途上にあり、自己制御力や論理的思考力は伸び盛り。
- 身体は第二次性徴を迎え、筋力や持久力が一気に高まる。
- 社会性では、協調性や自己主張のバランスを学び取る段階にある。
このため「新しいことを始めるのが遅すぎる」という心配は不要です。
スポーツなら高校や大学で力を発揮する選手も多く、芸術分野も中学からの挑戦で十分に開花します。
実際、私の知人の息子さんは中1から吹奏楽でサックスを始めました。
最初は音を出すのに精一杯でしたが、2年後には代表メンバーとして演奏会に立つまで成長。
思春期の吸収力は、スタートの遅れを補って余りあると感じました。

中学生から始めても成果を出している人は身近に多いものです。挑戦を遅らせる理由にはなりませんよ。
部活・塾と両立できる週あたり時間の目安
中学生の生活は、部活や塾で多忙になりがちです。
平日の放課後は部活動で1日2〜3時間、週に3〜5日が一般的。
さらに塾に通えば夜9時以降まで勉強、というスケジュールになることも珍しくありません。
この中で習い事に使える時間をどう確保するかがポイントです。
- 目安は週1回・1時間程度から。
- 平日は30分だけ自主練習、休日にまとめて数時間という方法も有効。
- 学校行事やテスト前は一時休止や振替が可能な教室を選ぶと安心。
知人の家庭でも、息子(中2)が英語教室と部活を両立しています。
平日は30分だけ復習、休日は2時間ほどオンラインで外国人講師と会話練習。
この「平日少し+休日集中」のスタイルで、勉強とのバランスも取れています。



両立のコツは「必ずこの曜日は習い事」と固定してしまうことです。家族全員で共通認識を持つと続けやすいですよ。
「遅くない」を後押しする“最小スタート”設計(週1・3ヶ月)
新しいことを始めるとき、人はどうしても腰が重くなります。
この心理を行動経済学では現状維持バイアスと呼びます。
だからこそ、始めるときは「とにかく負担を小さく」することが大切です。
- 頻度は週1回から。
- 期間はまず3ヶ月。
- ノルマは「行くだけ」で良い。
例えば、プログラミング教室に通う場合。
最初から毎日1時間コードを書くのはハードルが高いですが、「週1回教室に行くだけ」なら実行可能ですよね。
3ヶ月も通えば習慣化の兆しが見えてきます。
私の知人の娘(中1)はピアノを再開したとき、最初の目標を「週1回のレッスンに参加するだけ」と決めたそうです。
「練習は気が向いたら」でスタートしましたが、気づけば3ヶ月後には毎日15分は自分から弾くように。
小さな一歩が自然に習慣を生むと実感しました。
費用も同じです。
いきなり高価な道具を揃える必要はありません。
無料体験やレンタルで始め、続けられると感じた時点で徐々に投資すれば十分です。



最初から完璧を目指さなくて大丈夫です。「物足りないくらい」で始めるのが続ける秘訣ですね。
第2章|中学生におすすめの習い事【目的別カタログ】
ここからは、実際にどんな習い事があるのかを目的別に整理して紹介します。
中学生からでも十分に始められる「スポーツ」「武道・ダンス」「文化・表現」「STEM・語学」「eスポーツ・デジタル」。
それぞれに遅くない度や週あたりの目安時間を示しながら、体験談を交えてお伝えします。
スポーツ系の習い事|中学からでも伸びる競技が多い
特徴とおすすめ例
- サッカー:中学からでも部活やクラブで挑戦可。技術面は経験者に差があるが、体力や戦術理解でカバー可能。
- バスケットボール:体格や瞬発力が活きる。未経験でも練習次第で高校でレギュラーを狙える。
- 陸上競技:短距離・長距離とも中学デビューが一般的。個人競技のため成果が見えやすい。
- 水泳:選手コースは厳しいが、体力づくりや泳法習得は中学からでも十分。
- テニス(特にソフトテニス):多くが中学からスタート。高校でも続けやすい。
- 卓球・バドミントン:反射神経が活きる。初心者からでも短期間で成果が出やすい。
| 種目 | 遅くない度 | 週時間目安 | 大会・検定 |
|---|---|---|---|
| サッカー | ★★★★☆ | 週2〜3回 | あり |
| バスケット | ★★★★☆ | 週2〜4回 | あり |
| 陸上 | ★★★★★ | 週1〜3回 | あり |
| 水泳 | ★★★☆☆ | 週1〜2回 | あり |
| テニス | ★★★★☆ | 週1〜3回 | あり |
| 卓球 | ★★★★☆ | 週2〜3回 | あり |
| バドミントン | ★★★★☆ | 週2〜3回 | あり |
私自身、身長180cmの体格を活かして中学からバスケットを始めました。
最初は経験者との差に戸惑いましたが、フィジカル面ではむしろ有利に感じることも多かったです。
身体的な成長が大きい中学生期は「今から始めても遅くない」と実感しました。
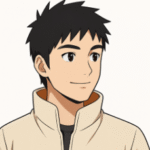
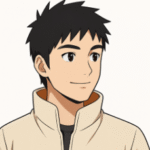
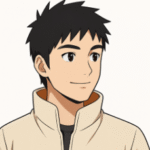
運動系は怪我リスクもあるため、体験時に安全管理をしっかり確認すると安心ですね。
武道・ダンス系の習い事|礼儀や表現力を磨ける
- 柔道・空手・剣道:段級制度があるため初心者も白帯から。努力次第で短期間に昇級可能。
- ストリートダンス:中高生から始める人が多い。音楽に合わせて自由に表現できる楽しさが魅力。
- クラシックバレエ(基礎):プロ志向には遅いが、姿勢改善や基礎的な柔軟性向上には最適。
私の甥(身長165cm)は中1から空手を始めました。
最初は白帯で年下の子と一緒に練習することに戸惑っていましたが、半年後には大会に出場し、自信を得たようです。
礼儀や集中力を学べる武道は思春期の子どもに特に効果的だと感じます。



初心者でも堂々とスタートできるのが武道やダンス系の魅力です。経験年数よりも継続する意志が大切ですね。
文化・表現系の習い事|感性と自己肯定感を育む
- 楽器(ギター・ピアノ再開・ドラム):軽音部との相性も良く、中学生から始めても十分楽しめる。
- 合唱や演劇:舞台経験が自己表現力を高める。声変わり後の中学生に適している。
- 美術・デザイン・マンガ・イラスト:作品として成果が見える。コンクールやSNS発信でモチベーション維持。
- 書道:集中力を養い、昇級制度で達成感を得やすい。
- 写真・動画編集:スマホ世代に親和性が高く、SNSや文化祭で成果を披露できる。
中学生から始めた私の教え子が、書道で高校生の段位を短期間で取得した例もあります。
知的好奇心や表現欲求が強い年齢だからこそ、文化系は中学からのスタートでも大きな飛躍が可能です。



「楽しさ」が続ける原動力です。資格や大会結果よりも、毎日の小さな達成感を大事にすると良いですよ。
STEM・語学系の習い事|将来を見据えたスキル習得
- プログラミング:中学生なら理解力が高く、数ヶ月でゲーム制作まで到達可能。
- ロボット教室・電子工作:ものづくり好きにぴったり。理数科目の理解も深まる。
- 3Dモデリング:デジタル表現力を磨ける。中学生からの挑戦でコンテスト入賞も可能。
- 英会話・ディベート:スピーキング力や論理構築力を鍛え、受験にもプラス。
私の知人はオンライン英会話を息子と一緒に受講しています。
15分の短いレッスンですが、週3回続けることで発音が改善し、自信を持って英語を話すようになっています。
語学やプログラミングは「短時間×継続」が効果を生むと実感しました。



最初から高い目標を設定せず、まずは週1回から始めると習慣になりやすいですよ。
eスポーツ・デジタル系の習い事|新時代の選択肢
- eスポーツ:競技志向だけでなく、チーム戦術やコミュニケーション力を育む場として注目。
- ゲーム実況・動画編集:発信力を鍛え、企画・表現力が磨かれる。
- 健康管理との両立:スクリーンタイムや休憩ルールを明確にして取り組めば、安心して続けられる。
私は実際にオンラインでのeスポーツスクールを見学しました。
講師がプレイ前に必ずストレッチを指導し、画面の見すぎによる疲れ対策もセットで教えていました。
楽しさと健全さを両立させる指導は、親としても安心できると感じました。



「ただのゲーム」で終わらせず、学びや交流の場にできるのがeスポーツの魅力ですね。
第3章|失敗しない始め方と比較の“型”
新しい習い事を始めるとき、最初の3か月間は「継続できるかどうか」を決める分岐点です。
この章では、体験レッスンから3か月までのロードマップ、比較表を使った判断基準、そして部活や塾との両立術を具体的にお伝えします。
中学生の習い事の始め方|体験→初月→3か月ロードマップ
体験レッスンで見るべき5つのポイント
体験レッスンは「お試し」だからこそ重要です。以下をチェックしましょう。
- 講師の指導法や人柄
- 子どもが場に馴染めているか
- 設備や安全管理が整っているか
- レッスン内容のレベル感
- 欠席振替や連絡体制の明確さ
私は息子と一緒に複数の体験に行きましたが、先生の声かけ一つで本人のやる気が大きく変わると実感しました。
子どもの表情が輝いているかどうかが最も信頼できる判断基準です。



体験後は「どうだった?」と聞くだけでなく、親自身の印象も共有してあげると安心して選べますよ。
初月は行動目標を設定する
入会した最初の1か月は、結果を追い求めるより「行動」を目標にするのがおすすめです。
- 毎回必ず出席する
- レッスンで一言は発言する
- 毎日5分だけ復習する
我が家では、娘がピアノを再開したとき「まずは休まず通う」を唯一の目標にしました。
小さな達成でも親がしっかり褒めることで、自然と次のステップへ進めました。



「頑張ったね」とプロセスを評価することが、子どもの自己肯定感を大きく高めますよ。
3か月で方向性を見直す
3か月経ったら続けるかどうかを判断します。
- 本人のモチベーションが上がっているか
- 何らかの上達が見えるか
- 生活リズムに無理が出ていないか
もし違和感があるなら教室変更や一時休会も選択肢に。
「やめる」ことが必ずしも失敗ではありません。別の可能性に出会うきっかけにもなります。



3か月間カレンダーに予定を固定しておくと、習慣化が加速します。これは行動科学でいうコミットメント装置の一つですね。
中学生の習い事の比較表と判断基準の作り方
複数候補で迷ったら、比較表を作って点数化すると冷静に判断できます。
| 評価軸 | 重み(1-5) | 候補A:サッカー | 候補B:プログラミング |
|---|---|---|---|
| 費用 | 3 | 2(やや高い) | 4(比較的安い) |
| 時間負担 | 4 | 3(週2回) | 4(週1回) |
| アクセス | 5 | 4(自転車15分) | 2(電車30分) |
| 指導内容 | 4 | 5(好印象) | 4(良さそう) |
| 本人の興味 | 5 | 5(大好き) | 3(PC好きだが未経験) |
| 将来へのつながり | 2 | 3(高校でも継続可) | 5(ITスキル習得) |
こうして点数化すると「納得感を持って選べる」効果があります。
親子で重みづけを一緒に決めることで、対話のきっかけにもなります。
口コミを調べる際も注意が必要です。
極端な意見に偏りがちなので、複数サイトで共通して語られる点を参考にしましょう。
また「先生が厳しい」「アットホーム」といった表現は人によって感じ方が違うため、必ず体験で自分の目で確かめることが大切です。



数字に表すことで、親の視点と子どもの希望をすり合わせやすくなりますよ。
部活・塾と習い事を両立するタイムテーブル
中学生は「時間のやりくり」が最大の課題です。以下の3つのスタイルを参考にしてください。
週1ペース
- 平日は部活中心
- 週1回だけ習い事を固定
- 休日に自主練習を補完
週2ペース
- 部活の休みを活用
- 平日1回+休日1回の習い事
- 睡眠不足にならないよう23時までに就寝
短期集中型
- 学期中は部活や勉強優先
- 長期休暇に短期講座や合宿で集中的に学ぶ
私の家庭では、息子が「週1ペース+長期休暇集中型」を選びました。
結果として、勉強や友達との時間を犠牲にせず無理なく続けられています。
オンラインを組み合わせる方法も有効です。
平日はオンラインで短時間、休日は対面でしっかり学ぶ。
移動時間が省けるので家庭の負担も減ります。



「頑張りすぎて燃え尽きた」ケースを多く見てきました。最初は余裕を持たせるくらいがちょうど良いですね。
第4章|続ける仕組みとQ&Aで意思決定を後押し
習い事は始めるより続けるほうが難しいものです。
この章では、継続のための行動デザイン、コミットメント装置、挫折の前兆と対処法、そして多くの保護者が抱く質問に答えていきます。
習い事を続けるための行動デザイン4ステップ
習慣を定着させるには、環境と仕組みづくりが欠かせません。
私は「やる気に任せる」のではなく、仕組みで支えることが鍵だと考えています。
- トリガー(きっかけ)を決める
夕食後すぐにピアノを弾く、通学電車で英単語アプリを開くなど、日常行動に結びつけます。 - 行動のハードルを下げる
「問題集1ページだけ」「ギターをリビングに置いておく」など、始めやすくしておくことが大事です。 - 即時フィードバックを仕掛ける
練習カレンダーにシールを貼る、アプリで連続記録を確認するなど、小さな達成感を見える化します。 - ごほうびを用意する
練習後にハーブティーを飲む、宿題を終えたらゲームを15分だけ遊ぶなど、即時性のある報酬をセットしましょう。
私の娘は、ピアノ練習後に「好きな曲を1回自由に弾いて良い」というルールを作ったところ、楽しみながら続けられるようになりました。



ごほうびは物でなくても構いません。達成直後に感じられる「快」を意識すると継続率が上がりますよ。
コミットメント装置でやる気を見える化する
行動を支えるもうひとつの工夫が、コミットメント装置です。
- 進捗ボード:検定級を階段状に書き込み、合格したら色を塗る。
- 学習記録ノート:練習した時間や内容を簡単に記録する。
- ペア学習:友達や家族と一緒に取り組む。
息子の場合、進捗ボードに「英検合格」「部活大会ベスト8」などを可視化しました。
壁に貼った目標が日々の励みになり、自然とやる気が持続していました。



人は「見える化」されると弱いものです。記録が増える喜びが継続を後押ししますね。
挫折の前兆と微調整で続けやすくする
どんなに工夫しても、やめたくなる瞬間は訪れます。
そこで挫折の前兆を早めに察知し、調整することが大切です。
- ステップが大きすぎる → 難しすぎて投げ出す前に、細かく区切って取り組む。
- 報酬が弱くなった → 初心者向けの検定を受けさせるなど、成功体験を増やす。
- トリガーが不安定 → ルーティンを再設定し、再び「固定された時間」で行う。
私は息子が「塾と習い事で疲れている」と口にしたとき、週2回を週1回に減らしました。
頻度を下げても継続するほうが、やめてしまうよりはるかに良い結果につながります。



やめるのではなく「微調整」する発想が大切です。柔軟に変えれば長続きしますよ。
中学生の習い事 よくある質問(FAQ)
今から始めても遅くない競技は?
中学デビューが普通の競技は多いです。
陸上や卓球、剣道などは遅すぎる心配は不要。
全国トップを狙うなら早期スタートが有利ですが、「楽しむ・上達する」という目的なら中学生からでも十分間に合います。



「やりたい」と思ったときがベストタイミングです。遅いかどうかより一歩踏み出すことが大切ですね。
おすすめを1つに絞る基準は?
まずは本人の強い関心を最優先にしましょう。
同程度なら「費用」「アクセス」など続けやすさで選ぶと失敗しにくいです。
親が決めるのではなく、最終判断は子どもに委ねることも大切です。



「自分で選んだ」という実感が、責任感や継続力を育ててくれますよ。
費用が合わないときは?
自治体のスポーツ教室や公的講座は安価または無料で利用できます。
学校の部活や地域の少年団も低コストです。
オンライン教材やアプリを組み合わせるのも良い選択肢です。



工夫次第で環境は整えられます。費用のせいで諦める必要はないですね。
受験期はどうする?
学業を優先しつつ、完全にやめず頻度を減らすのが現実的です。
休会制度を活用して一時的に止める方法もあります。
「合格したら再開する」と約束しておけばモチベーション維持にもつながります。



受験期に無理をして続ける必要はありません。細くても継続すればリズムは保てますよ。
最終チェックと次の一歩
決断に迷うときは、候補を3つに絞って〇△×で直感的に評価し、その理由を書き出してみましょう。
さらに、問い合わせ時に便利な雛形を活用するとスムーズです。
件名:〇〇教室 体験レッスン希望(中学〇年・氏名)
〇〇教室 ご担当者様
はじめまして。△△市在住の□□と申します。
中学〇年生の息子(娘)が、〇〇教室の体験レッスンを希望しております。
第1希望:◯月◯日(◯)◯時~
第2希望:◯月◯日(◯)◯時~
どうぞよろしくお願いいたします。
□□
最後に「習い事チャレンジ合意書」を作るのもおすすめです。
親子で目標やルールを決め、サインして壁に貼るだけで大きな効果があります。
私の家庭でもこれを実践し、「親も支える」「子も頑張る」という気持ちを共有できました。



始めたあとにズレが生まれないよう、最初に合意を取っておくと安心ですね。
まとめ章|中学生の習い事を成功に導く最終チェックリスト
ここまで読んでいただいた方は、「始めるのが遅くない理由」「目的別おすすめ」「失敗しない始め方と比較方法」「続ける仕組み」までイメージができていると思います。
最後に、行動へ移すための総仕上げチェックリストをまとめます。
習い事を決める前の最終チェック
- 中学生から始めても伸びやすい分野を理解できたか
- 目的(体力・実績・スキル・自己肯定感)が親子で共有できているか
- 時間・費用・送迎などのリソースを現実的に把握したか
- 候補を3つに絞り、体験予約を入れられたか
私は息子と一緒に候補を紙に書き出し、〇△×で直感評価をしました。
最終的に「本人が最もやりたい」と言ったものを選びましたが、その後の継続力がまったく違いました。



迷ったら「好き」を優先してください。やらされ感では続きにくいですよ。
習い事を始めてからの最終チェック
- 初月は行動目標(必ず出席、1日5分だけなど)を設定できているか
- 3か月後に見直すタイミングをカレンダーに入れたか
- コミットメント装置(記録ノート・進捗ボード)を用意したか
- 家族内で送迎やルールを共有し、協力体制を整えたか
娘がピアノを再開したとき、進捗ボードに「弾けるようになった曲」を書き出しました。
達成感が目に見えることで、本人も「ここまでできたんだ」と喜び、自然に次の曲に挑戦するようになりました。



成長の証を見える化するだけで、やる気の持続度が格段に上がりますね。
習い事を続ける上で忘れないこと
- 挫折は「悪」ではなく、微調整のサイン
- 頻度を減らしてでも継続するほうが価値は高い
- 受験期は休会や頻度調整で柔軟に対応
- 最終目的は「子どもの成長と幸福」であり、習い事はその手段
私自身も、「やめてもいい」と伝えたときに子どもが逆に「続けたい」と言った経験があります。
無理強いせず柔軟に寄り添う姿勢が、長く続けるための土台になるのだと感じました。



習い事はゴールではありません。子どもの未来を支えるプロセスそのものを大事にしてくださいね。
ここからは、ぜひ一歩行動に移してください。
体験レッスンの予約を入れて、カレンダーに書き込む。
その小さな一歩が、中学生の可能性を大きく広げるきっかけになります。
筆者からのご案内
本記事は、筆者が独自に行った調査や情報収集をもとに、筆者自身の主観的な評価や感想を交えて構成しております。そのため、記載の内容や見解はすべての方に当てはまるものではなく、また同様の結果を得ることやサービスをご利用いただけることを保証するものではございません。
情報の正確性・完全性・最新性については細心の注意を払っておりますが、内容を恒常的に保証するものではございません。
サービスや条件、仕様等は予告なく変更される場合がございますので、必ず公式サイトなどの一次情報をご確認いただきますようお願い申し上げます。
また、本記事の内容を参考にされたことにより生じたいかなる損害や不利益につきましても、筆者および本サイトは一切の責任を負いかねますことをあらかじめご了承いただけますと幸いです。
本記事は広告を含んでおりますが、いずれも読者の皆さまの追加的な情報収集及びご判断の一助となることを目的に掲載しております。
なお、当サイトはAmazonのアソシエイトとして、適格販売により収入を得ています。
価格は変動することがあるため、必ずリンク先のサイトまたは公式サイトで確認するようにしてください。
本記事はあくまで参考情報としてご活用いただき、必ず公式サイト等で情報をご確認のうえ、ご自身の判断で最終決定をしていただけますよう、心よりお願い申し上げます。



この記事が、あなたとお子さんの新しい一歩を後押しするきっかけになれば嬉しいです。
「やってみたい」という気持ちを信じて、一度体験に足を運んでみてください。
小さな挑戦が、大きな成長につながります。応援しています。
出典
文部科学省(公式)「中学校学習指導要領:武道・ダンス必修化」
スポーツ庁(公式)「運動部活動の在り方に関する総合的なガイドライン」
子ども家庭庁(公式)「令和7年版こども白書」
文部科学省(公式)「令和5年度 子供の学習費調査(結果の概要)」
子ども家庭庁(公式)「令和6年度 青少年のインターネット利用環境実態調査」









コメント